
裁量労働制(さいりょうろうどうせい)とは、労働時間を「実際に働いた時間」ではなく、会社が決めた「一定の時間」とする労働時間制度のことをいい、「みなし労働時間制」ともいいます。出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間に応じた残業代は発生しません。
この制度はどんな業種にでも導入できるものではなく、法律・厚生労働省令が認めた業種に限ります。本来は従業員が効率的に働くことができるための制度ですが、実労働時間に応じた残業が認められないことから、不当な長時間労働が発生するおそれもあります。
ここでは、裁量労働制の仕組みと、残業代請求の考え方などについて解説します。
裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の2つがあります。
専門業務型裁量労働制
実際の労働時間とは関わりなく、労使協定で定めた時間分働いたものとみなす制度で、業務の遂行手段や時間配分の決定において、使用者側が労働者に具体的な指示を行うことが難しい業務が導入の対象となります。デザイナーやシステムエンジニアなど、専門性の高い職種で19の業種に限定されています。
企画業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制と同様に、業務の遂行手段や時間配分の決定において、使用者側が労働者に具体的な指示を行うことが難しい業務が対象になっている点は同じですが、事業の運営にあたり、経営的にも重要な事業運営の企画、立案、調査及び分析の業務にあたる労働者に限定されています。
専門業務型裁量労働制よりも導入条件が厳しく、該当する職種として、経営企画や人事、財務管理など、本社機能に関する業務に携わる従業員があげられます。
ここでは、それぞれの裁量労働制の特徴や内容について解説します。

専門業務型裁量労働制が一般的な雇用形態と大きく違う点は、「みなし労働時間制」の採用です。みなし労働時間制は、実際に働いた労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間分を働いたと考える制度です。
労使協定のなかで「1日のみなし労働時間を8時間とする」と決めた場合、その日の実際の労働時間が5時間でも10時間でも、「8時間」と処理され、残業代は発生しません。
なお、「1日のみなし労働時間を9時間とする」と労使協定で決められた場合、8時間を超えた分の1時間は残業代が発生します。
その他にも、深夜労働や休日労働を行えば、裁量労働制でも残業代が発生します。
専門業務型裁量労働制を導入できる業務は、次の19種に限られています。
関連リンク
導入にあたっては就業規則の変更、雇用契約書の作成はもちろんのこと、対象業務や業務内容、みなし労働時間などを定めた労使協定を元に、労働基準監督署へ届け出をしなければなりません。なお、専門業務型裁量労働制の導入にあたっては、次の要件を満たす必要があります。
専門業務型裁量労働制の採用要件
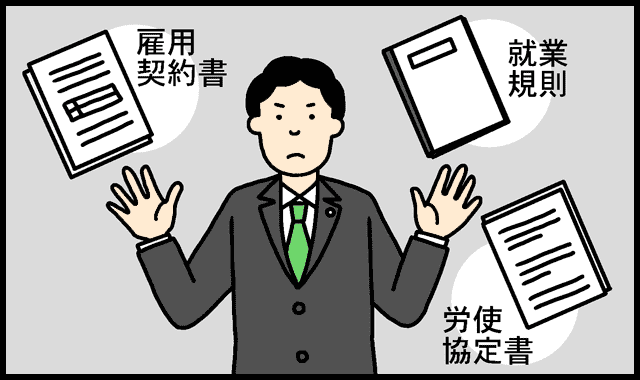
これらの要件を満たして労使協定を締結し、管轄の労働基準監督署長へ届け出(厚生労働省が提供している様式第13号に必要事項を記入・提出)を行います。
専門業務型裁量労働制の導入は、働き方や給与体系に大きく影響するため、労使で十分に協議し、慎重に進めなければなりません。

企画業務裁量労働制においても「専門業務型裁量労働制」と同じく、「みなし労働時間制」を採用した雇用制度となります。
この制度を導入できるのは「事業の運営に関する企画、立案、調査及び分析の業務」に限られるため、専門業務型裁量労働制のように業種が限定されているわけではありませんが、職種は限られます。
企画業務型裁量労働制は、専門業務型裁量労働制のように業種は限定されていませんが、企画立案や調査分析の業務は客観的判断のむずかしい業務であるため、企画業務型裁量労働制を導入するには厳格な条件が求められます。
企画業務型裁量労働制の採用要件(抜粋)
企画業務型裁量労働制の適用は、このような条件をすべて満たす必要があり、導入したとしている場合でも、条件を満たしていなければ無効となるケースも少なくありません。
無効となった場合には、実際に働いた時間を算定し、1日8時間、週40時間を超える労働には残業代を請求することができます。
裁量動労制を採用すれば、残業代が発生しないという誤解や誤った解釈をされることがありますが、裁量労働制を導入しているケースでも、次に該当するものは残業代が発生します。
みなし労働時間が8時間を超える設定の場合
みなし労働時間が1日8時間以内の場合は、実労働が10時間であっても割増賃金は発生しません。しかし、みなし労働時間が法定内の8時間を超える設定で取り決めされているとき、8時間を超える分については時間外労働として扱われるので残業代が発生します。
例えば、みなし労働時間が9時間の設定で合意している場合、8時間を超える1時間分は時間外労働とみなされます。
深夜労働・休日労働
いつ働いても、いつ休んでもよいというイメージのある裁量労働制ですが、休日は必ず設定しなければなりません。労使協定で定めた休日に働いた場合、やはり休日労働として割増賃金が発生します。また、22時から翌5時の深夜労働も労働時間数に応じて割増賃金が発生します。
専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制ともに導入にあたっては、就業規則の変更、雇用契約書の作成はもちろんのこと、対象業務や業務内容、みなし労働時間などを定めた労使協定を元に、管轄の労働基準監督署に届け出をしなければなりません。
導入できる業種に制限もあることから、会社の都合で自由に導入できる制度ではありませんので、一方的に導入を告げられた場合は違法性が高いと考えられ、注意が必要です。
裁量労働制とは異なりますが、「事業場外みなし労働時間制」や「フレックスタイム制」など、労働者の裁量に関わる仕組みが設けられた制度もあります。
これらの制度も正しい運用が行われずに残業が常態化しているようなケースでは、残業代を請求できる可能性があります。
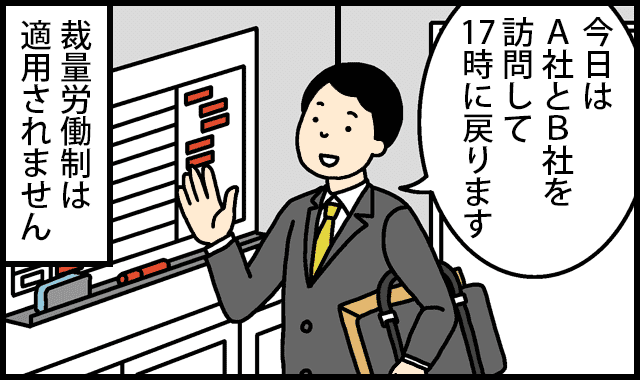
事業場外みなし労働時間制は、一定条件のもと、裁量労働制と同様に「みなし労働時間制」が採用されています。労働時間の正確な把握や使用者側の具体的な指示が難しい外回りの多い営業職(外交セールス)や旅行添乗員、雑誌などにおける記事の取材で1日のほとんどを社外で過ごしているなど、事業場の外で業務を行う際に導入できる制度です。
導入条件として「会社の外で業務を行っていること」「労働時間の算定が難しいこと」があげられ、社外で働いている場合でも、会社の責任者が同行していたり、訪問先や帰社時があらかじめ決まっている場合、労働時間の把握ができるため、この制度は適用されません。
現在では、携帯電話の普及や時間管理におけるクラウドシステムの導入をはじめ、zoomなどのオンラインMTGツールや、チャットですぐ連絡がとれる体制を構築している企業も多く、この制度を適用できるケースは少なくなっているかもしれません。
テレワークによる勤務が中心となるケースについては、一定要件を満たせばみなし労働時間制の対象となりますが、細かい条件もあるため、気になる方は厚生労働省・総務省が公開しているテレワーク総合ポータルサイトも確認するとよいでしょう。
関連リンク
事業場外みなし労働時間制の対象とならないケース
フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間をあらかじめ設定し、この範囲内であれば、労働者が仕事やプライベートの状況などを加味して自由に出退勤時間を決められることが特徴です。
企業によっては「コアタイム」を導入していることもあり、これは1日のなかであらかじめ出勤しなければいけない時間を決め、その前後にあたる出退勤の時間を自由に調整できる(フレキシブルタイム)仕組みです。
一定ルールのもと、労働者の裁量で自由な働き方が可能となることから、従業員のモチベーションアップには有効ですが、飲食などの接客業や工場勤務など、導入が難しい業種もあり、すべての企業で採用できるわけではありません。
フレックスタイム制は労働時間の自由度が高いように見える反面、企業側は実労働時間を正確に把握しなければならないため、みなし労働時間制を採用している裁量労働制とは似ているようで大きく異なる制度です。
関連リンク
高度プロフェッショナル制度はホワイトカラーエグゼンプションとも呼ばれ、一定以上の年収(1075万円以上)があり、高い専門知識が求められる労働者を対象に、労働時間ではなく得られた成果で評価される仕組みです。
対象が19職種・業務に限定され、弁護士などの士業やコンサルタント業務、金融商品の開発業務や証券アナリストなどが挙げられます。
この制度では、時間外労働をはじめ休日・深夜の割増賃金も発生しないため、この点は裁量労働制と大きく異なります。こうした点を考慮して、使用者側は労働者の健康確保に向け、決められた措置の実施を行わなければなりません。
働き方改革関連法により施行された制度ですが、国会審議の過程で「残業代ゼロ法案」との揶揄や批判・懸念もあり、導入には様々な条件や義務が課されることとなりました。
関連リンク
企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制は、基本的には仕事内容が「時間ではなく質」を求める職業に導入される制度です。そのため、従業員の能力が高ければ労働時間の短縮につながり、従業員にもプラスとなります。
しかし、企画業務型裁量労働制と専門業務型裁量労働制は、ともに導入条件が規定されていますので、規定に当てはまらない業種・職種で導入されていたり、運用規則が守られずに残業が横行しているようなケースでは無効となり、未払い残業代を請求できる可能性があります。
会社側が裁量労働制の運用を誤解・悪用している可能性があり、その場合はきちんと残業代を請求したいとお考えであれば、まず弁護士へ相談し、ご自身の状況を確認しながらどのように対応すべきか検討されることをおすすめします。

小湊 敬祐
Keisuke Kominato
働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。