交通事故における頸椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)の後遺障害
calendar_today公開日:
event_repeat最終更新日:2023年07月07日
部位別の後遺障害等級認定について交通事故による後遺障害について
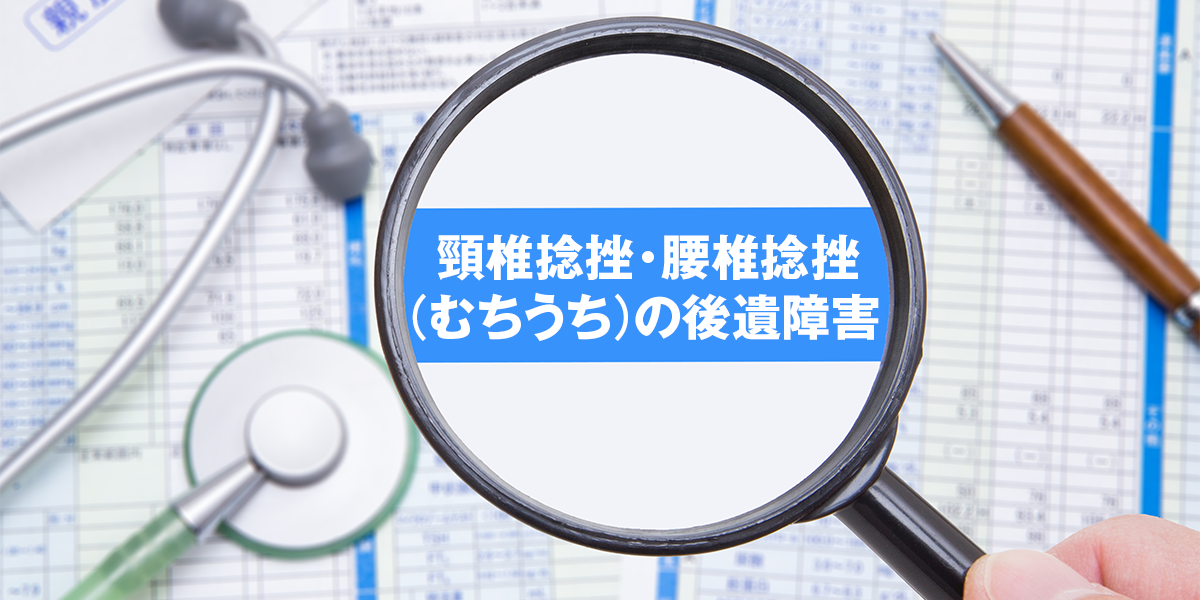
交通事故被害に遭われた方のケガで多く見受けられる「むちうち」の症状について、事故当時は身体に痛みがなかったものの、時間の経過とともに首や腰に痛みの症状が出てきたり、ときに頭痛やめまい、耳鳴り、吐き気、眼精疲労など、首や腰の痛みと直接関係のないような症状が現れることもあります。
むちうち症は、レントゲンなどで症状の原因を特定できないケースが多く、外傷のない場合、見た目ではケガの症状がわかりにくいことから、保険会社から治療費打ち切りを受けやすく、病状を軽視されてしまうことがあります。
ここでは、頸椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)の内容や後遺障害の等級について解説します。
- この記事の内容
むちうち症について
首や腰などに強い衝撃を受けることで起きる症状を総称して「むちうち症」といいます。医学的な正式名称ではなく、強い衝撃で首が「ムチのようにしなって」靭帯や筋肉、椎間板、関節包などを痛めてしまうことから「むちうち」と呼ばれています。
「むちうち症」は正式な傷病名ではなく、医療機関では「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」「頸部捻挫」「頸部損傷」などの傷病名で診断されます。また、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなどの症状が出る場合には「バレ・リュー症候群」という診断がなされることがあります。
むちうち症における後遺障害について
むちうち症における後遺障害の等級は、「12級」「14級」「非該当」となります。より重い症状として認定されるには、医学的な証明をどの程度できるかがポイントとなります。
MRIの診断内容で、第三者が見て分かるほどの医学的に客観的な証拠がある場合は「12級」、検査結果などにより「むちうち」を「証明」できないものの、治療経過などから「説明」できる場合には「14級」として認定される可能性があります。
医学的に証明も説明もできない場合、後遺障害は非該当となります。
むちうち症の後遺障害等級と認定基準
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 第12級13号 | ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・医学的に客観的な証拠があり、「むちうち」だと証明できる場合 |
| 第14級9号 | ・局部に神経症状を残すもの ・医学的に証明できなくても、治療経過などから説明できる場合 |
| 非該当 | ・症状を医学的に説明できない場合 |
むちうち損傷によって残存した症状が12級に認定されるか、14級に認定されるか、非該当とされるかは、慰謝料や逸失利益等に深く連動するため、後遺障害の認定は大変重要です。ただし、一定条件がある場合に自動で12級や14級になるというものでないため、この点は注意が必要です。
12級と14級の分かれ目は「他覚的所見」の有無です。「頑固な神経症状」という言葉を使いますが、必ずしも痛みやしびれの強さに着目して振り分けられるわけではありません。
自賠責保険の実務上、「障害の存在が医学的に立証できるもの」「医学的に証明し得る神経系統の機能または精神の障害が残っている」「感覚障害、錐体路症状及び錐体外路症状を伴わない軽度の麻痺、気脳撮影など他覚的所見により証明される軽度の脳萎縮、脳波の軽度の異常所見等が残っている」などの場合、12級の認定がなされます。
一例をあげると、脊髄から上肢に向かう神経根が圧迫されていることがMRI画像でわかる場合などが、他覚的所見のあるむちうち症に当たります。もっとも、画像上何らかの変性が確認される場合でも、事故によって生じた異常なのか、陳旧性のもの(事故前から生じていたもの)かがはっきりわからない場合もあり、画像で異常が出れば即ちに12級が認定されるというわけではありません。
むちうち症の場合、画像所見が得られないケースの方が多く、14級の認定を受けられるか非該当となるかの問題になることが多いです。
14級は「障害の存在が医学的に説明可能」「医学的に証明できないが、自覚症状が誇張でないと医学的に推定されるもの」という考え方が採用されています。
主訴しか存在せず、医学的説明ができないものは一般に非該当とされます。
なお、14級と非該当との違いについては、次の項目が考慮されると考えられます。
- 事故状況との関連性
事故によりある程度の強い衝撃が被害者の身体に加わったと認められることが必要です。車同士の事故で車体に軽い傷しかついていない場合や、逆突事故などの一般的に衝撃が弱い類型の事故の場合には、後遺障害が残る程の衝撃はなかったと判断されます。
- 受傷当時からの症状の訴えの「連続性」「一貫性」(自覚症状が一貫して継続しているか)
受傷後すぐから症状固定までの間、一貫した症状を訴えているかが重要です。例えば、事故当初は首の痛みのみを訴えて、事故から数か月経ってはじめて腰痛を訴えても、腰痛が後遺障害として認定されるのは困難です。
- 治療状況の推移(定期的な通院があるか)
週2〜3回(月10回)程度の通院を半年以上コンスタントに続けていることが必要です。「通院」に含まれるのは整形外科などの病院・クリニックのみで、整骨院に通った日数は評価されません。
- 検査内容(症状に応じた適切な検査を受けているか)
事故後速やかに画像検査を受けることが重要です。結果的に異常なしという結果でも、14級が認定されることがあります。骨に損傷がないむちうち症は、レントゲン写真からはわかりませんので、MRI画像を撮るようにしましょう。
- 後遺障害診断書の記載内容(症状改善可能性の有無)
後遺障害は、基本的に治療によって回復しない状態なので、症状が改善するという趣旨の記載があると等級認定は難しくなります。その他、痛みやしびれについては、常に症状があること(常時痛)が必要であり、「○○したときに痛む(動作時痛)」との記載しかない場合、非該当となります。また、後遺障害診断書上、記載されていない部位の痛み・しびれは、認定対象から外れてしまうため、症状のある全ての部位を網羅することが必要です。
むちうち症における「自覚症状」と「他覚所見」とは?
交通事故被害におけるむちうち症の示談交渉では、「自覚症状」「他覚所見」という言葉を用いることがあります。ここではそれぞれの意味について説明します。
- 自覚症状
被害者自身が訴えている症状です。後遺障害診断書でも「自覚症状」欄が設けられており、被害者からのヒアリング内容を踏まえて医師が記載します。
むちうち症の場合、外観や検査画像からは、症状がわからないケースも多いため、まずは被害者自身が感じている症状を正確に医師に伝えることが重要です。
- 他覚所見
第三者が見て客観的に捉えることができる症状です。
検査画像からわかる異常をはじめ、医師による触診・視診、各種の検査から異常が検知される場合には、他覚所見があるといいます。なお、自賠責保険の後遺障害認定においては、他覚所見の中でも画像による所見が特に重要視されます。
頸椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)の等級認定に向けた留意点について
頸椎捻挫・腰椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級認定は、通院をしっかり行い、適切な治療をきちんと受けていくことで、認定される可能性が高まります。ここではむちうち症の後遺障害等級認定を想定して準備すべきことや注意すべき点について解説します。
必要十分な頻度・期間の通院をすること
むちうち症の場合、必要十分な期間・頻度での通院が非常に重要です。明らかに傷や骨折がある場合と異なり、むちうち症では、画像その他の検査結果からは「痛い」という証拠を得られないケースが大半です。痛みが続いていることが医学的に説明できる、といえるためには、適切な頻度での通院を、半年以上継続することが必要です。
速やかに画像検査を受けること
症状がある部位については、事故から日をおかずに画像撮影をするようにしましょう。むちうち症の後遺障害認定にとってプラスに働くほか、万が一より重篤な傷害があった場合の早期発見と後遺障害認定にもつながります。
事故から時間が経っての撮影の場合、仮に異常が発見されても、事故との因果関係が否定されてしまう場合があるので注意が必要です。
症状を遺漏なく主治医に伝えること
症状は漏れなく主治医に伝えましょう。伝えた内容を診断書やカルテに記録してもらうことで、症状が一貫していること(事故当初から症状があり、現在まで残っていること)の証拠となります。また、万が一後からむちうち症以外の傷病が見つかった場合でも、事故当初から症状を訴えていたことが、事故との因果関係を証明する突破口になります。
事故当初に伝えていない部位に後遺障害が残った場合、認定を受けることが非常に難しくなりますので、症状は遠慮せずに伝えましょう。
交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください
この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。
弁護士三浦 知草
-
上野法律事務所
- 東京弁護士会
- 弁護士詳細
