離婚における子どもの親権・監護権について
calendar_today公開日:
event_repeat最終更新日:2023年12月21日
離婚に関する子どもの問題について
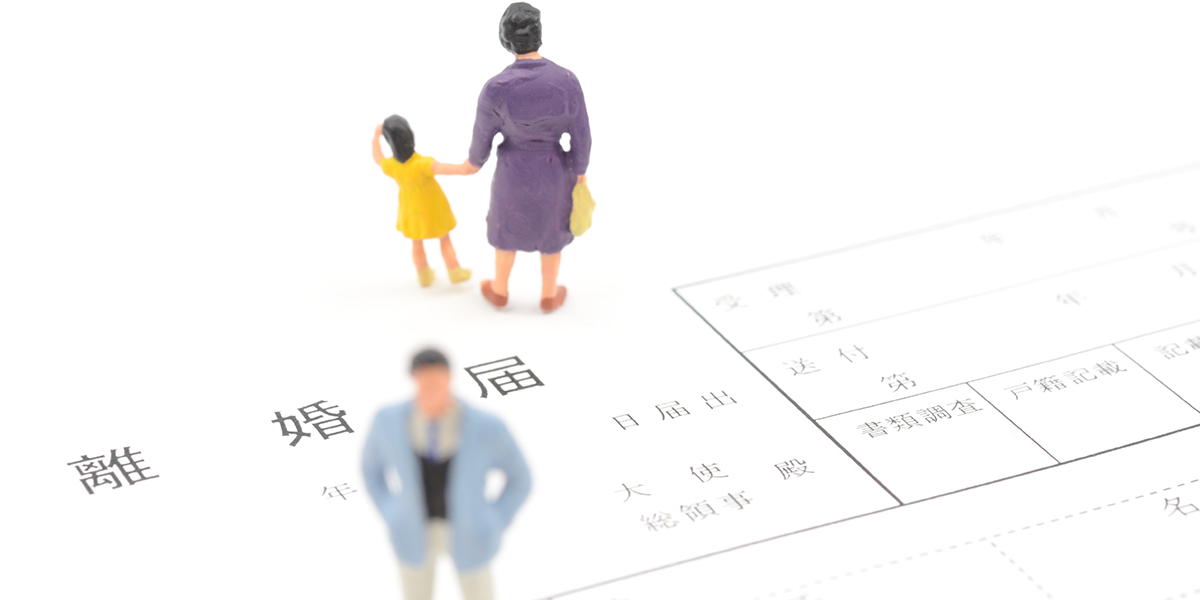
離婚において未成年のお子さんがいる場合、どちらの親が子を引き取り養育するのかを決めなければなりません。
親権者の記載欄が空白のままでは、役所で離婚届を受理してもらうことができないため、事前に親権を決める必要があるのですが、親権を巡ってはどちらの親も獲得を主張し揉めることがよくあります。
ここでは、親権の内容や親権を決めるための流れ、親権に対する裁判所の考え方などについて説明します。
- この記事の内容
-
親権とは?
親権とは、子を監護・教育するために父母に認められた権利義務です。大きく分けて、「財産管理権」と「(身上)監護権」の2つに区別されます。
父母の婚姻中は、共同親権が採用されており、原則として、父母で共同して親権を行使することとされています(民法818条3項)。
一方、離婚後は、単独親権の制度がとられています。父母が離婚する場合には、どちらかを親権者としなければならず(民法819条1項・2項)、親権者を決めなければ離婚届は受理されません(民法765条1項)。
親権者は、子の養育について、包括的で広範な権限を有することになります。
他方で、親権者でない親の権利義務として認められているのは、面会交流や養育費といったものにとどまります。
このような子に対する立場の差異の大きさから、父母の両方が親権を強く希望し、争いになることも多いのです。
財産管理権とは?
親権者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する「財産管理権」を有しています(民法824条)。
親権者は、子の財産の処分について包括的な代理権を持ちます。例えば、未成年者名義の不動産がある場合に、賃貸したり、抵当権を設定したり、売却したりする処分を、ほぼ自由に行うことができます。
例外的に、親権者は、自身と子の利益が相反する行為を行うことはできず、子に「特別代理人」をつける必要があります。
例えば、未成年者と親権者の間で財産を売買することや、ともに相続人になって遺産を分割することは、利益相反行為に当たります。
監護権(身上管理権)とは?
親権者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利義務である「監護権(身上監護権)」を有しています(民法820条)。
「監護」とは、子が成長するうえで必要な一切の行為を指し、衣食住を与えたり、子が病気やケガをしたときに診療を受けさせたりすることを含みます。
「教育」は、知育・徳育・体育など、子の成長に必要な教育全般を指し、家庭教育と学校教育の両方を含みます。
令和4年12月の民法改正では、親権者による子への懲戒権(旧822条)の規程が削除されるとともに、新たに「親権を行う者は、前条(820条)の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。」(民法821条)という規程が設けられました。
子の利益を十分に尊重し、適切に監護すべきという、親権の義務としての側面が重視されるようになっています。
以下、監護権に含まれる個々の権利義務について見ていきます。
- 居所指定権
子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならないとされています(民法822条)。
- 職業許可権
子は、親権者の許可を得なければ、職業を営むことができないとされています(民法823条1項)。また、いったん職業を営むことを許可した子であっても、その営業に堪えることができない事由がある場合には、親権者は職業の許可を取り消したり、制限したりすることができます(民法823条2項、6条2項)。
- 身分行為に関する事項
15歳未満の子が普通養子縁組を行う場合、親権者は子に代わって縁組の代諾をしたり、離縁の協議を行ったりすることができます。なお、15歳以上の子については、自ら縁組をすることが可能です。
以前は、未成年者の婚姻(男性18~19歳、女性16~19歳)が認められていたことから、婚姻についての親の同意の問題もありました。しかし、令和4年4月の民法改正により、成人年齢と婚姻年齢がともに18歳とされたため、この問題は解消されました。
- 命名権
明文の規程はありませんが、親権者は子に名をつける権利を有するとされています。
- 子の引渡し請求権
親権者(または監護権者)ではない第三者が、子をその支配下に置いている場合、親権者は、親権の妨害排除請求として、子の引渡しを求めることができます。
離婚後、非親権者となった親やその親族が、子の引渡しを拒否する場合などが、権利行使の典型場面です。
親権者と監護権者の違いについて
離婚においては、親権者とは別に、子の監護・教育のみを行う監護権者を指定することができるとされています(民法771条、766条1項・2項、人事訴訟法32条1項)。また、事後的に、監護権者のみを変更することも可能です(民法766条3項)。
例えば、親権者を父としつつ、監護権者を母として、実際に子と同居・養育を行うのは母とするといった形が考えられます。
親権と監護権を分属させる場合には、親権者と別に監護権者を定めることが子の利益に適うかという観点から判断がなされます。
もっとも、家庭裁判所が、親権者と監護権者を分けて定めることは稀です。
親権と監護権を分けるメリット
父母が互いに親権を主張して対立が激しい場合に、親権と監護権を分けることで、お互いに譲歩しあって合意することが可能になることがあります。
また、親権を持てない側の親は、「子との繋がりがなくなってしまうのではないか。」と不安を感じていることが多いため、子に関する権利の一部を持てることで、安心感に繋がるといえます。
親権と監護権を分けるデメリット
子に関する意思決定を行う際に、父母がいちいち連絡を取り合って判断を行わなければならず、父母の間で意見が対立して意思決定がうまく進まないことがあり得ます。特に、一方の再婚相手と子との養子縁組をする際には、他方の同意が必要になるなど、トラブルになることが多くなります。
また、親権者/監護権者がそれぞれ有する権利義務の内容について、当事者間で誤解やズレが生じていることに気づかないまま合意がなされ、後々トラブルが生じることもあります。
なお、面会交流の実施や養育費の確保を期待して親権と監護権を分けるケースもありますが、親権・監護権が分属したからといって、必ずしも面会や支払いが確保されるわけではありません。
子とのつながりがあるという心情的な面を除いては、親権者と監護権者を分けるメリットはあまりなく、トラブルになる懸念の方が大きいといえます。家庭裁判所においても、親権・監護権の分属を積極的に推奨はしていません。
主に子の監護をしてきた当事者の方は、「子が自分のところにいればよいから、監護権だけあればよい」と安易に考えず、きちんと親権の獲得を主張する方がよいといえます。
また、非監護親の側は、戸籍上の親権者になるという形にこだわるよりも、継続的・確実な面会交流の確保など、実体的な子とのつながりを重視して手続きを進めることも検討すべきでしょう。
親権者を決定するための流れ
未成年の子がいる場合、親権者を決めずに離婚をすることはできません。そのため、離婚届を提出する前にどちらの親が子を養育するかを決めなければなりませんが、親権をめぐってはトラブルになることがよく見受けられます。ここでは、親権を決定するための流れについて説明します。
離婚協議の中で親権者を決める
まずは離婚協議のなかでどちらが親権をとるか話し合いを行います。それぞれに主張があると思いますので、冷静に話し合いができる状況であれば、お互いの気持ちを確認した上でよく協議をし、親権を決めます。
なお、離婚協議で、親権者と監護権者を分ける合意をすることはおすすめしません。すでに述べたようなトラブルになる可能性があります。また、親権者は戸籍を見ればわかりますが、監護権者はそうではないので、非親権者側の監護権をおおやけに証明できるものがないことで、トラブルにつながるおそれもあります。
調停で親権者を決めるための話し合いを進める
当事者同士の協議で合意することができない場合には、家庭裁判所へ調停申立てを行います。
調停で親権者を決める場合、離婚調停の中で、離婚に関わるその他の要素とともに協議されるのが一般的です。
当事者双方が親権者になりたいと主張する場合、いずれが親権者として適切かについての主張・立証を行います。双方が「子の監護状況に関する陳述書」を作成し、自分の生活状況・子の監護方針・監護補助者の状況・子の成育歴や監護の実情などをまとめて提出することが多いです。加えて、母子手帳や幼稚園・保育園の連絡帳・おくすり手帳など、子の健康状態や発達状況のわかる資料の提出を求められます。
また、親権が中心的な争点になっている事件では、家庭裁判所調査官による調査が行われることも一般的です。
調査官は、以下のような調査を行い、その結果を調査報告書としてまとめます。
- 父母との個別の面談
- 家庭訪問(自宅での親子の様子や監護環境等の確認)
- 子との面談(意思表示が可能な年齢の子の場合)
- 幼稚園や保育園への照会
15歳以上の子の場合、子の意見の聴取は必須とされています。それ以下の年齢でも、意見の確認がなされ、その意見が尊重されることが通常です。子の発育・発達状況にもよりますが、意見表明ができる年齢の目安は10歳前後です。
調査報告書では、調査官が監護権・親権についての意見を述べます。この意見は、裁判官の判断にも大きな影響を与えます。
調停での話し合いの結果、親権者を父母いずれとするかの合意ができ、離婚のその他の要素についても意見がまとまった場合には、調停が成立します。当事者同士の主張・立証だけでは親権について譲歩しなかった当事者も、調査報告書に記載された子の心情や調査官の意見を見て、合意に応じるケースがあります。
親権の他、離婚の可否や財産分与等について意見がまとまらない場合には、調停は不調(不成立)となり、終了します。親権者決定の争いは、離婚訴訟に移ります。
また、親権者決定のいわば前哨戦として、非監護親の側から、子の監護者指定・子の引渡しの調停・審判または保全手続きが申し立てられることもあります。
親権者を決める際には、監護の継続性が重要な要素となるため、離婚訴訟で時間をかけて親権を争っていると、監護を行っていない親はどんどん不利になっていく傾向があります。そのため、早い段階で子を自分で監護すべく、子の監護者指定・子の引渡しの請求が行われるのです。
子の監護者指定・子の引渡し事件でも、親権者指定とほぼ同じ要素が検討されます。監護者として指定された親のその後の養育に特に問題がなければ、監護親と同じ親が、離婚訴訟で親権者に指定されることが多いといえます。
訴訟で親権者を決める
調停が不調になった場合、離婚を求める側は、改めて離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚訴訟では、主に書面でもって、親権者にどちらがふさわしいかの主張・立証がなされます。調停と異なり、協議を行う場面はあまりありませんが、一通りの主張・立証が尽くされたタイミングで、裁判官から心証の開示がなされ、和解をすすめられることが多いです。和解ができない場合には、必要に応じて尋問が実施され、最終的には判決で親権についても結論が出されます。
訴訟においても、親権者の判断要素は調停とほぼ同じですが、調停の記録が引き継がれるわけではないので、必要な資料は改めて当事者から提出する必要があります。
なお、離婚訴訟においては「調停前置主義」がとられているため、合意が困難なことが明らかな場合であっても、いったん調停を申し立て、不調にしたうえで訴訟を起こす必要があります。
審判で親権者を決める
親権者の指定は、通常は離婚訴訟で扱いますが、「調停に代わる審判(24条審判)」によって親権者が指定されることもあります。
調停に代わる審判では、調停からそのまま記録が引き継がれて審判に移り、裁判官が親権者についての結論を決めます。審判結果に不服がある場合には、2週間以内に異議を申し立てることで、効力がなくなります。
もっとも、実務では、異議が出そうな場合に調停に代わる審判が出されることはほとんどなく、あらかじめ当事者が審判内容に合意しているケースで行われるのが一般的です。例えば、調停成立には当事者双方の出頭が必要であるところ、一方の当事者が遠方に居住してこれまで電話で調停に参加していたような場合、調停成立のために裁判所に来ることは大きな負担になります。
このような場合、調停に代わる審判を用いることで、当事者が出頭しなくても、親権者の決定を行うことができます。
また、民法は制度として親権者指定の審判(819条5項)を定めていますが、実務で利用されることは稀です。
裁判所における親権を決めるための判断基準について
裁判所が親権者を決める際の視点は、「子の利益に適うかどうか」です。
具体的には、以下のような要素を総合考慮して判断します。
- 親の監護能力
- 家庭環境
- 居住・教育環境
- 子に対する愛情
- 従来の監護状況
- 監護の継続性
- 監護補助者の有無や状況
- 子の意思
- 子の年齢・性別
- きょうだい関係
- 子の心身の発育状況
- 従来の環境への適応状況
- 環境の変化への適応状況
- 父母や親族との結びつき
この中でも特に重要といわれるのが、監護の継続性と子の意思です。以下、各要素についてご説明します。
監護の継続性の基準
裁判所は、「当事者が監護者・親権者として不適切でないか」を検討します。もっとも、当事者双方とも監護者・親権者適格に問題がない場合に、「監護者・親権者としてより優れているのはどちらか」を判断するわけではありません。
どちらにも大きな問題がないのであれば、裁判所は、子の現状を維持することを優先して判断を行います。なぜなら、監護者がむやみに変更されてしまうと、子が精神的に不安定になってしまうからです。
このため、親権者を決めるうえでは、監護の継続性の基準が非常に重要になります。
子の意思尊重の基準
家庭裁判所で親権者・監護権者を決める際には、15歳以上の子の意見を聞くことが必須とされています。また、それ以下の年齢の子でも、通常は家庭裁判所調査官が意見を聴取し、意見を尊重しながら判断がなされます。個人の発育・発達状況によりますが、だいたい10歳前後から、有効な意思表示が可能と考えられています。
子が親権者に望んでいる親が明らかに監護者として不適切な場合は別ですが、双方に大きな問題がない場合には、子の意見は重要な判断要素となります。
ただし、特に子の年齢が低い場合、監護親に迎合しやすいので、親の影響を受けた意見を話していないかには注意する必要があります。
その他の要素について
以下、親権者を決めるうえで考慮される、その他の要素について見ていきます。
- 母性優先の原則
母性的・母的な役割を果たす親を優先するとする基準です。
かつては「母親優先の原則」ともいわれていましたが、現在では、単に母親(女性)であるだけで親権者適格を認めることは少なくなっています。主に父親が子の監護を担っている場合には、母性的な役割を担っているのは父親とされ、父親が親権者とされる可能性が高くなります。
もっとも、現在でも育児負担が女性に偏っている夫婦が多いため、事実上女性側が親権者とされるケースは多いといえるでしょう。
- きょうだい不分離の原則
子が幼い場合には、きょうだいで親権者を分離するのは相当でないとする基準です。絶対的なものではなく、補助的な基準の1つといえます。
また、子が意思表示可能な年齢に達している場合には、きょうだいそれぞれの意思を尊重して、一方を母、他方を父に分属させることもあり得ます。
- 面会交流の許容性
相手方との面会を許容することは、補助的な要素として、親権獲得にとってプラスに働きます。離婚後も、両親から愛情を受け、交流できることが子の利益に適うという観点によるものです。
- 奪取の違法性
監護開始の違法性が大きい場合には、必ずしも監護を継続している側が親権者となれるわけではありません。例えば、相手方がすでに単独で監護している子を勝手に連れ去ったり、面会交流に来た子を監護者のもとに帰さないといったことが、違法な連れ去りの典型例です。
単独での監護を開始する際には、相手方とあらかじめ協議を行うなど、適正に対応することが重要です。
主張されることが多いが決定打にならない要素
親権や監護権を争う事案では、相手方の親権者適格を否定するための主張がなされます。
ここでは、当事者からよく出る主張であるものの、親権者の判断にとっては決定的ではない要素についてご説明します。
- 相手方には子を養育するだけの経済力がない
父母の収入格差は、基本的に監護者・親権者を決める上で重要な要素にはなりません。
収入の高い側の当事者から、「相手方は主婦(主夫)やパートタイマーで収入が十分でなく、私が監護した方が子のためになる」というような主張がなされることがありますが、経済的な問題は、収入の高い側から低い側に養育費を支払えば解決できることも多く、親権の帰すうを左右することは稀です。
また、「相手方は浪費家だから親権を渡せない」という主張も認められないのが一般的です。浪費を主張する場合には、遊興によって子の養育がおろそかにされているといった一歩踏み込んだ主張・立証が必要になります。
- 相手方には監護補助者がいないので適切な監護は無理である
子の養育を援助してくれる親族などを「監護補助者」といいます。特に子が幼少のうちは、急な発熱など突発的な事態への対応も多く、監護補助者はいる方が望ましいといえます。もし監護をサポートしてくれる人が身近にいるのであれば、あらかじめ協力を依頼しておくといった対応は重要です。
もっとも、主に子の養育を行うべきは、あくまでも監護者・親権者である父母自身です。監護補助者は、その名のとおり、あくまで補助的・二次的な立場といえます。そのため、各種の公的サービスの利用や勤務先の理解を得ることによって、子の養育に必要な体制をとれているのであれば、監護補助者がいることは必須ではありません。
逆に、子の監護を祖父母などの監護補助者に任せきりにして、父・母自身が監護を怠っている場合、親権者を決めるうえでマイナスに働くおそれがあります。
- 同居時の家事や育児に不手際があった
同居時において、「相手方が家事を手抜きしていた・手際が悪い」「子にゲームやアニメを好きにさせる」「子の勉強をみてあげない」といった主張がなされることがあります。
もちろん、ネグレクトのような不適切な育児状況があれば、親権者として不適格だという判断がなされますが、単に当事者が不満に思っていたという程度の状態であれば、親権者の判断にさほど影響しません。特に、主張を行っている当事者の側が、育児への関わりが薄かった場合には、かえって「相手方の方が(不十分ななりに)育児を一手に担っていた」という心証につながる可能性もあります。
- 合意なく子連れ別居している
子連れ別居をする場合には、父母で事前に協議し、子を連れていくことについて合意しておくのが望ましいといえます。
もっとも、相手方が単に合意なく子を連れて出て行ったというだけでは、違法な連れ去りとまでは認められないことが通常です。
- 相手方は不貞をして夫婦関係を破綻させた
配偶者による不貞行為は離婚事由であり、慰謝料の請求原因にもなりますが、不貞をしていることそれ自体は、親権者適格を否定する要素にはなりません。
単に不貞行為をしたというのみならず、
- 不貞相手に会うために子を放置して夜間外出していた
- 子が在宅しているのに自宅で不貞行為をしていた
- 嫌がる子を無理やり不貞相手に会わせていた
といった、不貞が子の福祉に悪影響を与えたといえる事情を主張・立証できてはじめて、親権者の判断を左右する事情になりえます。
このように、配偶者である当事者自身に対する不誠実な行為があったという主張は、直ちに親権者適格を否定する要素に当たらないことには留意すべきです。
なお、子の見聞きしている前で配偶者へ暴行や脅迫を行う「面前DV」は、直接的な子への虐待(心理的虐待)に当たりますので、親権者として不適切とされる要素となります。
親権獲得に向けて留意すべきポイントとは?
ここまでご説明した親権者決定の考慮要素を踏まえ、親権を争う際には以下のような点に気を付ける必要があります。
子の福祉を最優先すること
親権を争う場合、なによりも子の福祉を重視することが必要です。
親権は、第一次的には、子の利益のためのものです。令和4年12月の民法改正でも、親権の親の権限としての側面よりも、子の利益のためのものという色彩が強められました。
親権の争いは子への愛情ゆえのことであっても、父母の紛争に巻き込まれた子は、心理的に大きな負担を感じます。
例えば、
- 子の前で相手方の悪口を言う
- 「お父さんとお母さんどちらがいい?」と子に選択を迫る
- 子が相手方との面会を望んでいるのにこれを拒否する
- 面会交流の際に子に探りを入れさせ、相手方の情報を知ろうとする
- 相手方に言いたいことを子に伝達させる
といった言動をとると、子は父母の間で板挟みになり、大きな葛藤を抱えてしまいます。
家庭裁判所も当事者のこのような言動を問題視しており、親権者として望ましくない言動と判断されます。
子を争いに巻き込むのは最小限とし、子の意思を十分に尊重するようにしましょう。
監護の継続の重要性
親権が獲得できるかどうかは、監護の継続性により大きく左右されます。
同居している間、明らかに相手方よりもご自身の育児参加が少なかった場合には、親権を獲得することは困難なケースが多いです。
相手方が親権を譲ることに合意した場合や、相手方が子を連れずに1人で別居し時間が経っている場合、子自身が「お父さん/お母さんがいい」とご自身を親権者として希望する意思表示してくれる場合には、親権を獲得できる可能性がありますが、そうでないケースでは難しいことが多いでしょう。
「自分は家族のために頑張って外で働いていたのに。」というお気持ちになる方も多いですが、親権争いの場面においては、そのような事情は考慮してもらえないのが通常です。
また、別居後、単独での監護になってからは、特に監護の継続性が重要です。相手方が違法に子を連れ去った場合にも、子が相手方の監護下で精神的に安定している期間が長くなり、子自身も相手方との暮らしを望むようになると、こちらが親権を獲得できる可能性は低下してしまいます。違法な奪取があった場合には、速やかに子の引渡し・子の監護者指定を求める手続きを行う必要があります。可能な限り早期に弁護士に相談しましょう。
相手方を誹謗中傷しないように注意すること
親権を争う場面では、お互いに相手方の親権者としての適格性を否定する主張を行うことが多くなります。もちろん相手方による不適切な監護実態を主張・立証することは必要なのですが、当事者は親権獲得に必死になるあまり、相手方や監護補助者である相手方親族を、誹謗中傷するような主張を行ってしまうこともしばしばあります。
父母が離婚しても親子関係は終わりになるわけではなく、面会交流や養育費支払いは、子がおとなになるまで続きます。子の成長や状況の変化に応じて、父母で連絡をとらなければならないケースも出てくるため、不用意に相手方の悪感情を刺激するような主張をし過ぎると、その後のやり取りが難しくなってしまうことがあります。また、父母の争いを目の当たりにした子自身も、父母の板挟みになることにストレスを感じ、非監護親と接触することに後ろ向きになってしまうこともあり得ます。
暴力やネグレクトといった虐待があるようなケースでは、毅然とした主張を行う必要がありますが、一方で感情的になりすぎず、冷静な主張を行うことも必要です。
離婚成立後の親権者変更は難しい
子の利益のために必要があると認められるときには、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができるとされています(民法819条6項)。
親権者が安易に変更されることは子の福祉に反することから、親権者変更には、手続面でも実体面でも慎重な対応がとられています。
まず、手続きについては、当事者同士の合意による変更は許されておらず、必ず家庭裁判所での調停・審判を経ることが必要です。
実体については、離婚時の親権者指定で考慮される要素に加えて、相当程度の「事情変更」が認められることが必要です。また、申立てがなされた動機や、当初親権者を決めた際の合意内容なども考慮されます。
親権者を変更すべき事情変更とされるのは、親権者による子への虐待(暴行、ネグレクト、性的虐待、精神的虐待など)、親権者が重篤な傷病で監護ができない状況になっていること、当初から子が戸籍上の親権者ではなく非親権者と生活をしていて実態と戸籍を合わせる必要があること、子自身が親権者変更を希望していることなどです。
親権者変更が認められるだけの事情変更の要件は、かなりハードルが高く、子が大きな問題なく相手方のもとで生活している場合にはほぼ認められません。
また、親権者変更は、子の福祉のために行われるものであるため、「子の幸せのため」ではなく、「自分のため」「相手方への腹いせのため」といった動機での申立ての場合、変更が認められる可能性は低くなります。
なお、子が親権者の再婚相手と養子縁組をしている場合、親権者変更の手続きをとることができなくなります。この場合、養親との離縁の訴えを行うか、または、養親の親権停止・親権喪失の手続きを行うことを要しますが、いずれも簡単には認められないといえます。
このように、当初取り決めた親権について、後から覆すことはかなり難しいといえます。仮に、離婚前に自分が監護者だった場合でも、親権者となった相手方のもとで子が問題なく生活していれば、変更は認められないことが多くなります。
離婚時に親権を決める際には、安易に相手方の主張を飲むのではなく、しっかり対応を行うことが重要です。
現在の親権を巡る社会状況について
日本では、長らく離婚後の単独親権が行われてきましたが、
- 単独親権制度が親権争いや子の連れ去りの原因になっていること
- 欧米では共同親権が一般的であること
- 離婚後の面会や養育費支払いの継続を確保する必要があること
といった事情から、共同親権の導入について議論がなされるようになってきました。
現時点では法改正の見通しは立っていませんが、令和4年11月、法制審議会において、共同親権の導入に関する中間試案が出されました。この中間試案では、共同親権か単独親権かを離婚の際に選択できるようにする案と、現行の単独親権制度を維持する案の両方が併記されています。また、令和5年2月までパブリックコメントが募集されました。
共同親権制度の創設により、子と非親権者との交流や養育費の確保ができることに期待が持たれている一方で、離婚後もDVや虐待の被害から脱出できないことへの懸念も示されています。
法改正があれば、親権についての大きな転換点となりますので、今後の議論を注視していく必要があります。
離婚において親権で争いがある場合は弁護士に相談する
親権の争いは、0か100かの結果にならざるを得ないこともあり、離婚において最も激しい争いになりやすい類型であるといえます。当事者同士で争う場合、子の連れ去りといった違法な行動が行われることもありますし、そうでなくとも、配偶者やその家族を激しく非難する主張をしてしまうことが多く、泥沼の争いに発展しがちです。また、親権は、本来子の幸福のために決定するべきものですが、父母の激しい争いによって、子を傷つけたり、離婚後の親子関係に悪影響を与えてしまうおそれもあります。
親権獲得に必要な主張・立証はしっかりと行いつつ、離婚後の面会や養育費支払いを見据えて、ときには紛争からのソフトランディングを図ることも考えておかなければなりません。
お子さんへの愛情や配偶者への怒りといった感情の絡む親権争いにおいて、当事者ご自身が冷静な対応を行うことは難しい場合も多くあります。ご自身の味方になる立場でありつつも、第三者でもある弁護士に依頼することで、よりよい解決ができることがありますので、親権について争いになるときには、ぜひ一度弁護士に相談してみましょう。
離婚・不貞に関する問題は弁護士へご相談ください
この記事の監修

離婚・不倫は、当事者の方を精神的に消耗させることが多い問題です。また、離婚は、過去の結婚生活についての清算を図るものであると同時に、将来の生活を左右するものであり、人生全体に関わる問題といえます。
各問題を少しでもよい解決に導き、新しい生活をスタートさせるお手伝いができれば幸いです。
弁護士三浦 知草
-
柏法律事務所
- 千葉県弁護士会
- 弁護士詳細
